

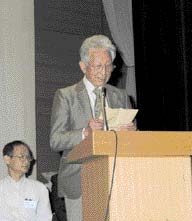 |
|
| 特別功労賞受賞スピーチ 矢崎秀彦氏 | |
| 本日は、本校創立85周年を記念いたしまして、このような盛大な紫友同窓会が開催されますこと、おめでたく心からお祝い申します。 さて、この佳き日に、私が著しました書物「寒水伊藤長七伝」にたいしまして「小石川賞・特別功労賞」をご授与賜りましたこと、まことに思いがけない幸運、ありがたく光栄至極に存じます。この本につきましては、伊藤長七先生のご生涯の全体にわたり詳述した著作として粕谷一希先生から高いご評価をいただきました。この席から改めて御礼申し上げます。 寒水先生のご生家は、私の家とは50メートルほどのご近所でして、先生のことは幼い頃から、東京の有名な中学校の校長先生と聞かされていました。諏訪中学の生徒の頃は、東に高き八ヶ岳 西にはひたす諏訪の湖に始まる七節からなる校歌を、これぞ近所の長七先生作と、いささか得意で声を張り上げました。 さて、伊藤長七先生の生き様を追跡してまいりますと、諏訪中学で大運動会などのとき、高々と掲げて士気高揚をはかる大幟に千万人といえども吾往かんという孟子の言葉がありますが、先生はまさしく、この言葉そのままの実践者であられたと、つくづく思えてくるのでした。この大幟の言葉は、清陵高校となった今でも彼らの気概となっているものですが、長七先生の言葉ではなく、大正13年諏訪中学校学友会の要請を受けて諏訪教育界の元老、両角恭四郎が、孟子からとって大書したもので、長七先生とは全く関係がありません。先生がこの言葉を口にされたことなども聞いたことはありません。しかし、私は、先生の伝記を書くに当たり、この言葉を第一部、長野県時代の副題とし、なお第二部の、本校校長時代を通じて、つまり先生の全生涯は、まさに「自反而縮雖千万人吾往矣」の実践者であられたと、感慨深いものがあります。 また「立志・開拓・創作」は、東京府立第五中学校創立以来、伊藤校長先生の高らかに掲げた教育モットーであり本校において見事な開花を見せ、みずみずしい成果を実らせ、伝統となって永続的な相貌を示しています。私はこのモットーを本書第二部の副題といたしましたが、この思想は先生青年時代に抱懐の萌芽が次第に育成され、ここに開花結実したものでありました。 「立志」については、諏訪高等小学校訓導時代に、岩波茂雄が杉浦重剛の日本中学校入学を希望したとき、片親となっていた茂雄の母を、「農家の跡取り息子を他郷に出すとは……」との親戚の非難から守るため、長七先生の家から上京させ、茂雄は長七の 男子志を立て郷関を出づ・・・ 青年至る所に青山あり の朗吟に送られた(阿倍能成)などにも、また小諸の児童の同級会を「立志同級会」と命名するなど、伊藤先生とはなじみ深く、立志はそもそも先生ご自身の立志でありました。 また、「開拓・創作」については、例えば長野師範学校卒業時に、後輩北沢種一に書き与え、学友多数の座右の銘となった言葉、「校風を造る人たれ、造らるる人たるなかれ、時勢を造る人たれ、造らるる人たるなかれ」などは、創作・開拓の原点の思想に他ならず、本書第一部時代から自覚され、主張された指導原理でありました。 さて、少し話は変わりますが、伊藤長七先生は、幼年の頃、少年の頃は、大変優しい温順なお人柄であったといいます。その頃、女の子に顔を赤らめて謝った話が語り伝えられています。ところがそれが師範学校2年生の頃、「豹変して」、「牧者に導かれる羊が猛虎になった」と、小学校から高等師範学校まで共にした矢島音次が語っています。これなど日清・日露の戦争に大勝した日本の国運を感じ取った先生の自己改革でありました。 以来、長七先生に一貫して特徴的な、あの世界の動向を見極めた達識の言動をもって、世界の木鐸の生涯を構築されたのでありました。 さて、終わりに一言私事を付け加えさせていただきたく存じます。 このたびの紫友同窓会は1919年(大正8年)創立以来85周年の記念の会ということでございます。実は私はその3年前の1916年(大正5年)4月の生まれです。それで同じ数え方をいたしますと、本年八十八歳の米寿となります。といたしますと、このたびの受賞は、私にとりましては米寿の祝いと重なることになります。不思議な喜びを、寒水伊藤長七先生は私にお与え下さいました。紫友会の皆様、本当にありがとうございます。 |